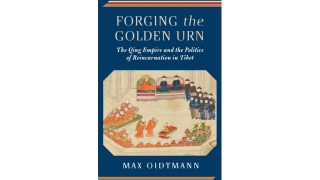1959年3月、中国はラサで行われた抗議活動を数千人の市民を殺害することで鎮圧し、1951年に自らも署名した協定を破ってチベット政府を解散させ、チベットを中国の省に組み込んだ。この事件を皮切りに、中国共産党は国際法を無視し、世界の抗議に虚偽報道を捏造することで応じる政策を採用するようになった。
マッシモ・イントロヴィーニャ(Massimo Introvigne)

2019年は1959年のチベットの動乱から60年の節目の年となる。この事件は、人権 を侵害し、国際法を堂々と無視する 中国共産党 の歴史において決定的なターニングポイントとなった。現在 新疆ウイグル自治区 で起きていることは、理論上1950年代にチベットで始まった政策の延長線上にある。中国共産党にとっては、党の思想的な関心の追求は国際的なイメージや広報活動よりも重要だ。国際社会に批判されると、中国共産党はまず虚偽報道の捏造を始める。
ラサの戦いについて、中国語とチベット語が分からない世界の読者が今まで知らなかったことの多くが、現在『苦悩するチベット: ラサ 1959年』(Tibet in Agony: Lhasa 1959)の英語版で知ることができる。著者の李江琳(リ・ジャンリン)氏は中国人の歴史学者であり、米国の大学院で学び、現在も米国在住である。ハーバード大学出版局が2016年に出版したこの書籍は、2010年に彼女が台湾と香港にて中国語で出版した著書の最新拡大版であり、この分野において最も正確で優れた研究書である。
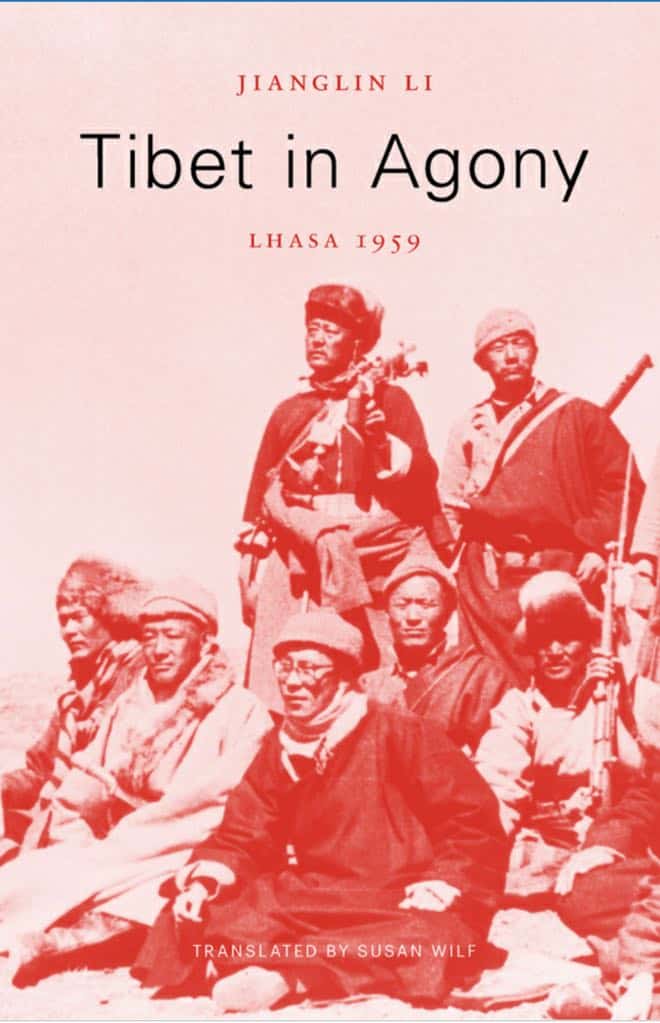
李氏は重要なポイントとして、チベットに関する多くの誤解は、地理の知識が不十分であるために生じているとしている。チベットとは何だろうか?大半の住民がチベット語を話し、チベット仏教を信仰している地域がチベットなら、中国がチベット 自治区 と呼ぶ地域の領土はその半分を占めることになる。従来アムドとカムと呼ばれていた地域が含まれる、もう半分のチベットは、現在、青海 省、甘粛省、四川省、雲南省に分割されている。このより大きな領域は地理学者と歴史学者から「民族的チベット」、現在のチベット自治区は「政治的チベット」と呼ばれている。1950年の中国によるチベット侵攻以前に、チベットが法的に独立国家であったかどうかに関しては、歴史上にも司法上も複雑な問題がある。ただし、当時のチベットが事実上は独立しており、ダライ・ラマとその政府が統治していたことに疑問の余地はない。この意見は現在のチベット自治区(および中国が1950年に占領し、政治的チベットから分離させたチャムドを含む)の領土にも言及している。中国共産党が1949年に政権の座を獲得する以前、中国とチベットは双方ともにアムドとカムの統治権を主張していたが、どちらも実際に統治していたわけではなかった。この2つの地域は、仏教の僧院の院長または世襲の部族により、多数の小さな区域に分かれて、治められていた。
李氏が言及した文書により、毛沢東(1893–1976)は主席就任以来、チベットの全ての領土を奪い、中国の省とする決断を下していたことが明白になった。しかし、国際社会の批判を避ける、または、限定するため、徐々に、辛抱強く実施するべきだと助言していた。
第一に、毛沢東は文化と宗教の面ではチベットに属すものの、ラサにあったチベット政府の統治を受けていないアムドとカムの統治を始めた。既に中国は、アムドとカムを自らの領土として複数の省に分割していたものの、実際には、従来の支配層が統治していた。しかし毛沢東はこのとき、従来の支配構造を整理し、共和制の理論を共産主義的な慣例に変えた。
第二に政治的チベットは6つの主要区域と首都のラサで構成され、最も東の区域はカムと隣接し、チャムドと呼ばれていた。1949年に政権の座に就くと、毛沢東はチャムドがチベットの一部ではないという中国の過去の主張を変え、ラサの統治に抗するチャムド人民解放委員会の設立を計画した。 1950年10月、中国人民解放軍 はチャムドに侵攻し、チャムド解放委員会の統治の下に自治を宣言した(後にチベット自治区の一部となる)。
1950年、毛沢東は中国の軍隊をラサに侵攻させるには時期尚早であると判断していた。小規模で、貧弱な軍備のチベット軍に恐れをなしたのではなく、国際社会の反応を恐れたためだ。しかし、チャムドの占領はチベット人に明確なメッセージを送ることになった。1951年にチベットは十七か条協定を強制的に結ばされるのだが、この協定の主なポイントは3つある。第一に、チベットはチベットが中国の一部であることを認める。第二に、内政においては、チベット政府と伝統の宗教社会構造が引き続き統治し、外交は中国が管理する。第三に、チベットは 中国軍 のラサへの大規模な駐留を許可し、中国共産党はチベットの域内で自由にプロパガンダを実施できる。
1950年、15歳だった現在のダライ・ラマは、優秀な若者で、様々な事柄の習得も早かったが、まだ学生の身分であり(1959年の時点では最後の学科試験の準備をしていた)、助言者や相談役、聖職者に頼らなければならなかった。現在では、そのうちの数名が実は中国共産党の二重スパイであったことが明らかになっている。李氏の著書の中にもあるように、ダライ・ラマは最後まで中国共産党と交渉可能だと信じていた(ある意味、亡命後も交渉可能だと考えていた)。李氏は、当時のチベットの人々、そして、その後の研究者のなかで、毛沢東の戦略を明確に理解している者はほとんど存在しなかったと指摘している。最近になってようやく、重要な文書が公開または漏洩されるようになった。
毛沢東は1950年代半ばより、カムとアムドから民族的チベットの「中国化」に着手した。その結果、100年続いた社会構造は破壊され、数名の伝統的な統治者が逮捕または処刑された。さらに、多数の仏教僧院が閉鎖に追い込まれ、一部は取り壊された。欧米の歴史学者は、カムとアムドへの残虐で時期尚早な中国化が現地で暴動を起こすことや(何千もの人々がゲリラ活動に参加し、低レベルの装備にもかかわらず、中国側に多大な犠牲者をだした。この抗中ゲリラ組織は、カム地方の別称に由来するチュシ・ガンドゥクの信仰の防衛軍と呼ばれた)、政治的チベットでの中国共産党への反感が巻き起こること(新たに中国化された地域から難民が逃亡を始めた)を毛沢東が予期しなかったとして、この時期の一連のチベットへの対応は失敗であったと長らく考えていた。
しかし、李氏が発見した文書からは正反対のことが明らかになった。毛沢東は意図的にカムとアムドで暴動が起きる状況を作り出し、反中国の暴動が政治的チベットでもすぐに起きることを心から願っていた。暴動が暴力的あればあるほど毛沢東にとっては好都合であった。そうすれば、チベットを占領し、ダライ・ラマの政府を排除したことに関し、後に、国際社会に中国軍とラサの市民を「反動的な無法者」から守るためだったと訴えることができるためだ。毛沢東の極秘のやりとりからは、中央政府が暴動を引き起こすよう指示していたにもかかわらず、暴動を防ごうとした現地の中国共産党の指導者が、毛沢東に何度も叱責を受けていたことが判明した。
後に中国の共産主義者の歴史学者が主張するほど、毛沢東は博識ではなかった。当初、ダライ・ラマが海外に逃亡する可能性があるという現実を重視していなかったものの、最終的には逃亡を阻止するよう命令している。ダライ・ラマは護衛の勇気とヒマラヤ山脈を知り尽くしていたおかげでインドに逃げることに成功した。毛沢東が寛大であったためではない。また、毛沢東は数年にわたり欧米諸国がチベット侵攻に対してどのような反応を示すのか確信が全くなかった。しかし、1957年までに安心できる材料を2つ得ていた。第一に、1956年、西欧諸国にはるかに近い東欧のハンガリーへのソビエトの侵攻に対して行動を起こさなかった。そして、最近になって公開されたインドの文書により明らかになったように、インドのジャワハルラール・ネルー首相(1889–1964)が、インドはこの問題に干渉しないことを毛沢東に保証しただけでなく、米国のドワイト・アイゼンハワー(Dwight D. Eisenhower)大統領(1890–1969)からもチベットをめぐって戦争を起こすことはないと伝えられていた。
そのため、1950年代の終わりには毛沢東はカムとアムドの仏教徒による反乱をできるだけ残虐に弾圧するよう命じ、僧院を爆撃して、神聖な仏像を破壊させただけでなく、ラサで暴動が起きることを期待して、政治的チベットの中国共産党の代表者と諜報員に挑発を拡大するよう指示した。1958年6月24日、毛沢東は機密文書のなかで、中国共産党は「チベットでの大規模な反乱を期待していて、規模は大きければ大きいほど好ましい」と述べていた。
挑発のなかには、中国共産党がダライ・ラマを誘拐し、北京に連行するという噂を広める行為もあった。この作戦は功を奏し、若きダライ・ラマが1959年3月10日に中国軍の司令部で行われる中国舞踊のショーへの招待を受けると、中国共産党が誘拐を実施するという噂が山火事のようにラサで広がっていった。大勢の群衆がノルブリンカにあったダライ・ラマの住居に集結した。中国軍司令部を訪問させないようにするためだ。中国軍に対して発砲は一発も行われず、初日の抗議活動の犠牲者は群衆に見つかり、殺害された中国共産党寄りの政治家のみであったが、群衆は反毛のスローガンを叫んだ。
しかし、チベットの住民と、国際社会全般(中国人の「お友達」を信頼せず、常に諜報活動を行っていたソ連とインドを除く)に気づかれることなく、毛沢東は既に国共内戦と朝鮮戦争を経験した有能な戦士から成る強力な軍隊を作って政治的チベットのすぐ外側に配置し、侵攻の詳しい計画を練っていた。これは、毛沢東がたとえ何が起きようとも3月10日以前のチベット侵攻を決断していた証拠といえる。3月10日から20日にかけてラサでは緊張が頂点に達した。中国軍はチベットの歴史ある宮殿や僧院を砲撃する準備が整っていることを公然と誇示した。ゲリラ組織のチュシ・ガンドゥクが山岳地帯からラサに到着したが、これも毛沢東が望んでいたことである。毛沢東はこれを、ネズミを広い場所におびきだし、皆殺しにする「昔の中国の作戦」と呼んでいた。ラサでは19世紀のライフルや大砲しか入手できなかったが、僧侶や市民もこれらの旧式の武器で武装した。
ダライ・ラマはまだ交渉が可能だと考え、中国軍の司令官に謙虚な手紙をしたためたものの、毛沢東は「自己防衛」を国際社会に訴えるため、チベット側が「先に発砲」するのを待ってから、攻撃を仕掛けるよう指示を出していた。しかし、毛沢東の期待通りにはいかなかった。ラサの中国軍の司令官であった譚冠三(タン・グアンサン)将軍(1908–1985)は脅威を感じ、想定していたチベット側の発砲を待つことも、中国からラサに向かっていた援兵を待つこともなく、3月20日に後にチベット動乱と呼ばれることになる行動を起こした。譚将軍は複数のチベットの寺院と離宮ノルブリンカを含む歴史的建造物を砲撃し、チベット軍の兵士や民兵、自分の身を守ろうとした市民を容赦なく殺害した。寛容な態度を示すことは稀な毛沢東だが、中央政府の指示を受けずに行動を起こした譚将軍に罰を与えず、チベットの抵抗の息の根を止めた残忍なやり方を称賛した。しかし、譚将軍とチベットの主な協力者たちは、文化大革命 中にこの過去の罪のツケを払うことになった。譚将軍は迫害を受けたものの、何とか生き延び、後に名誉は回復された。一方、チベット動乱の際にチベットにいた中国共産党のその他の主な重要な人々は全員処刑された。
チベット動乱は4日間で終わった。中国軍が旧式の武器を持つ農民や僧侶を駆逐するのは簡単であった。ただし、チベット側は、ダライ・ラマをどうにかインドへ安全に亡命させることだけは成しえた。ダライ・ラマは今もインドに留まっている。チベット人の犠牲者数は、軍事機密として今でも厳重に秘されているが、数千人に達すると考えられている(ただし、中国のプロパガンダは数百人程度と主張している)。おびただしい数のチベット人が逮捕および追放され、刑務所内で死亡した者もいる。
ラサの戦いは、チベットの伝統と自治に終止符を打ち、ダライ・ラマ政府を解散させ、信教の自由を取り上げ、政治的チベットを中国の省に変えて、横柄に、また誤解を招きかねない「自治区」に名称を変更した。また、中国共産党の歴史を研究している者や、民族や宗教の少数派に対する現在の弾圧を分析する者に2つの重要な教訓を与えた。第一に、中国共産党は国際的に大きく評判を貶めるとしても、政策を遂行することだ。1956年にハンガリーで起きた出来事から、西側諸国が派兵し、「ハンガリーのために死ぬ」ことを望んでおらず、ましてラサや新疆に派兵することなどは現実的にはないことを共産党は確認した(ベトナムへの派兵は別の問題であり、より複雑な事柄である)。第二に、中国共産党は単純に世界の抗議を無視するわけではないことだ。経験から虚偽報道のキャンペーンを展開する方が、戦争を仕掛けるよりも安く、簡単であることを知っているのだ。
1959年にはインターネットもソーシャルメディアもなかった。しかし、中国共産党は中国独自のストーリーを世界に伝えることに比較的成功していた。チベット側が一方的に反乱を開始し、大勢の人々がダライ・ラマの反動政府に操られたという虚偽報道が世界に広がった。毛沢東は反乱を引き起こすためにあらゆる手を尽くし、ダライ・ラマとその政府は反乱を阻止し、交渉するためにあらゆる手を尽くしていたため、この報道は真実とは正反対であった。ただし、中国共産党のプロパガンダでさえストーリーの全てを信じさせることはできなかった。中国国外では、ダライ・ラマが「反動主義者」により「拉致」されたという主張も、毛沢東が寛大に逃亡を手助けしたという主張に誰も耳を傾けなかった。しかし、アメリカ中央情報局(CIA)が反乱を組織したといったデマは今でもWikipedia等に掲載されている。CIAは確かにチベットに関心を持ち、1957年には沖縄とサイパンでチュシ・ガンドゥクの6人のメンバーを訓練し、そのうちの5人にラジオをもたせてパラシュートでチベットに降下させた(1人は自分の足を誤射し、沖縄に残った)。任務は反乱を組織し、先導することよりも、中国政府が作った情報のカーテンを突き破り、状況をCIAに直接報告することであったため、ラジオは絶対に必要であった。
李氏の著書は多くの虚偽報道の誤りを暴く上で有効なツールといえる。しかし、はるかにアクセスしやすい中国のプロパガンダと比べ、どれほど多くの人々がハーバード大学出版局により出版された学術書を手に取るだろうか?